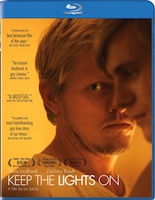
“Keep the Lights On” (2012) Ira Sachs
(アメリカ盤Blu-rayで鑑賞→amazon.com、日本のアマゾンでも購入可能→amazon.co.jp
)
2012年のアメリカ製ゲイ映画。NYに住む二人の男性の出会いと、10年近くにわたる関係をリアルに淡々と、しかし情感豊かに描いた内容。
主演は『誰がため』などのデンマーク人男優、トゥーレ・リントハート。
ベルリン国際映画祭テディ賞受賞。
90年代末、NYに住むドキュメンタリー映画作家のエリックは、ゲイがセックス相手を探す伝言ダイヤルで、大手出版社に努めるポールと出会う。二人の相性は良く、エリックはポールに連絡先を渡すが、彼は「自分にはGFがいる」と断る。
しかしポールはGFとの関係を清算し、エリックと付き合うようになり、やがて二人は一緒に暮らすようになる。ハッピーな関係に見えた二人だったが、実はポールにはドラッグの習慣があり、やがてそのことが二人の関係に次第に影を落としていき…といった内容。
ストーリーとしては、特にドラマチックなイベント的なことが起きるわけではなく、エリックとポール、そしてその周囲の友人たちや家族などの、些細だが極めてリアルで細かなエピソードが積み重ねられ、9年間(だったかな?)に渡る二人の軌跡が淡々と綴られるというもの。
何よりそのリアリティと、淡々としながらもゆったりとした空気感が素晴らしく、描かれるのは些細なことだけながらも、見ていて全く飽きさせず。作為の感じられない作劇と、ディテールのリアリズムと柔らかな空気感は、昨年の東京レズビアン&ゲイ映画祭で上映された、アンドリュー・ヘイ監督の傑作『ウィークエンド』とも似たテイスト。
興味深いのは、いわゆる恋愛テーマの映画では、惚れた腫れた憎んだ裏切っただのといった、恋愛感情の起伏が主に描かれるのに対して、この映画の場合は、互いに相手のことを好きであるにも関わらず、その間にリレーションシップを築いていくことの難しさにフォーカスが当たっているところ。
これは周囲の人間に関しても同様で、エリックがポールと一緒に生きる関係を築くことで悩むように、エリックの女友達もまた、最適のパートナーに巡り会えって自分の理想とするものを手に入れることができない。そんな誰でも身に覚えがありそうなリアルな「思い」を、ふわりと描いているという感じ。
というわけで、作為性のないドラマ作りが好きで、しかもこの空気感を心地よく感じられる人だったら、気に入ること間違いなし。いわゆるゲイ映画的な枠を越えた、単館上映系の映画のクオリティの高さがあるというあたりも、前述の『ウィークエンド』と同様。
ただ、大きな事件は何も起きないけれども、微細な起伏を丁寧に描いて、それが面白いという点では、ムードを音楽に頼っている部分も多く、そういう意味では、ヌリ・ビルゲ・ジェイラン監督作品ほどのストイックで厳格な凄みはないし、ストーリーのタイムスパンが長い分、『ウィークエンド』ほどの濃密さはありません。
とはいえ、クオリティの高さや全体のリアルな空気感は、好き嫌いはあるにせよ、間違いなく一見の価値はあり。エロティックな場面も生々しく、しかし心地よい空気感を持続したまま描かれているし、ラストの余韻も上々。
ゲイ映画好きの方、単館上映系が好きな方、そして、好きだからこそ関係を築く難しさという普遍的なテーマに興味のある方には、がっつりオススメしたい一本。
[amazonjs asin=”B009PJ1S5S” locale=”JP” title=”Keep the Lights on Blu-ray (2012) Import”]
[amazonjs asin=”B009PJ1Q82″ locale=”JP” title=”KEEP THE LIGHTS ON”]

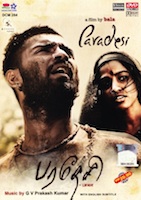
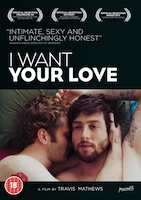


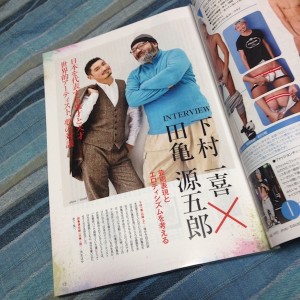
![Badi (バディ) 2014年 02月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51WX2ph76SL._SL160_.jpg)
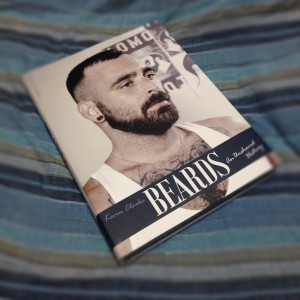
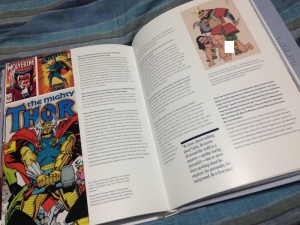
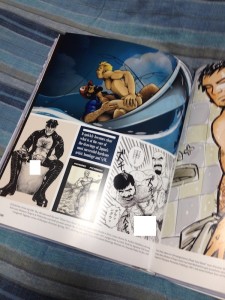
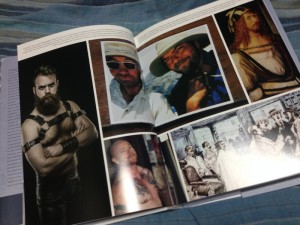
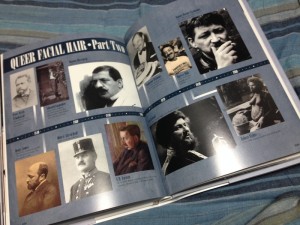
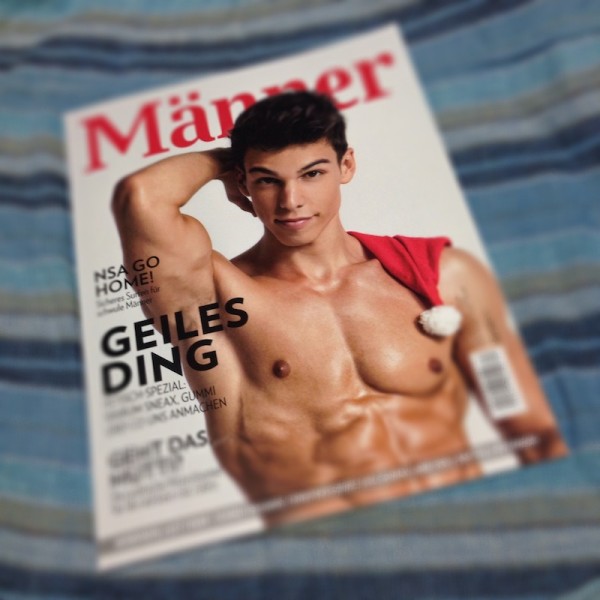
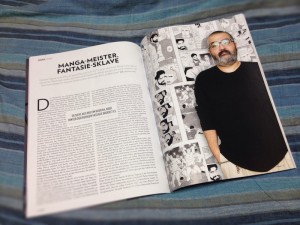

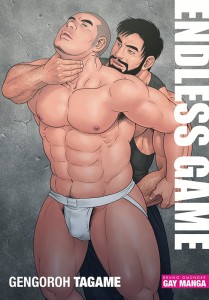

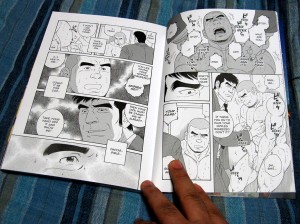
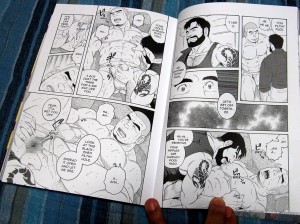
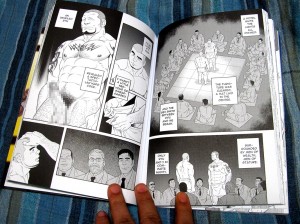
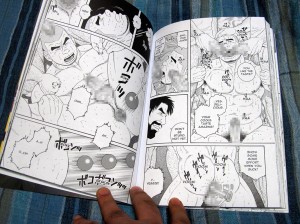
![Badi (バディ) 2014年 01月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51Ome1f38mL._SL160_.jpg)