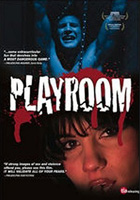
“Playroom (a.k.a. Consequences)” (2006) Stephen Stahl
アメリカのファンから「きっとコレ好きだよ」と薦められて、米盤DVDを購入してみました。
ストーリーは、幼馴染みの悪ガキ5人組が、やがて成長してそれぞれ家庭も持った後、フットボールの試合を見に行こうと、久しぶりで5人一緒によその街に繰り出して、ついでに学生気分に戻って馬鹿騒ぎをしていると、別行動したガタイ自慢で女好きの2人が行方不明になってしまい、やがて恐ろしい事件へと発展していく……というもの。
まあぶっちゃけた話、映画そのものは、はっきり言ってロクでもない出来です。カメラも演出もシロウトくさいし、ストーリー自体にも新味はない。
映画のジャンルとしては、おそらく、サスペンス風味とホラー風味があるアングラなアート系……ってとこなんでしょうが、どれもこれも大した才気は感じられない。いちおう、行方不明になった2人がどういう目にあっているかということと、その行方を捜す残りの友人たちとその家族といった要素が、2本並行して進んでいくんですが、特に後者に関しては、話にしても演出にしても実にひどい出来映え(笑)。
と言うと、何だか見るとこナシのクズ映画みたいなんですが、前者の行方不明になった2人に関してのみ、実はかなりヘンタイ指数が高くて、そそられる内容なんですな。このピンポイントだけで、DVD購入した価値があるくらい(笑)。
というわけで、以下ネタバレ承知で、ヘンタイポイントのみ解説します(笑)。
まずこの2人、顔も良ければ身体もマッチョと、なかなかの上物。キャラクターとしても、ガタイ自慢で女好きの体育会系バカノンケ(あ、褒め言葉よ、これ)って感じが良く出ている。
そんな2人が、怪しい女たちに誘われて、一夜の浮気を楽しむんですが、これまた、二組一緒に同じ部屋でバコバコ犯りまくるという具合で、バカノンケ度がタップリ。
ところが、一夜明けたら、2人ともベッドに手錠で拘束されていた。最初は、女たちの悪ふざけかと思い、ゲラゲラ笑ったりしていた2人ですが、そこに初老の男が現れて風向きが変わる。
実はこの男は、ヘンタイ映像作家で、2人のノンケは彼の作品の「主演男優」になるのだと告げられる。部屋には他にも、レザーの全頭マスクの犬男がいたり、ロッカーの中にアダルトグッズがビッシリだったりして、ヘンタイムードがタップリ。
とうぜん怒り狂う2人でしたが、手錠で繋がれているので抵抗もできず、初老の男に胸に跨られて「私にキスしろ」と迫られたり、身体をあちこち撫で回されたり。

そんなこんなで、いよいよ撮影がスタート。
2人は巨体の用心棒たちに連行され、部屋の一角にあった鉄棒状のラックに、うつぶせで脚を大きく開いた状態で、2人並んで拘束されてしまう。背後では、昨夜2人のアバンチュールの相手だった女たちが、股間にペニバンを装着。
こうして、怒りと恐怖に怒号をあげる2人の肛門を、後ろからペニバンがブッスリ。女たちは、そのままズコバコ腰を使い、アナルレイプされる2人は泣き叫ぶ。
もちろん、ポルノ映画ではないので、結合部のアップとかはないんですが、このペニバンレイプのシークエンス、あれこれアングルを変えながら、尺もたっぷりとってネチっこく続く。犯される2人の熱演もヨロシク、かなりのド迫力。

哀れ肛虐されてしまったノンケ2人は、事後屈辱に打ちひしがれる。
1人は何とか強がってみせる余裕は残っているものの、もう1人は身も世もなくオンナノコみたいに号泣。
しかしそれも束の間、容赦なく第2ラウンドがスタート。
ヘンタイ映像作家が取り出したのは、1本の金属製のディルド。「これは電流が流れる仕掛けになっていてね」と説明しながら、ディルドを金属製のベッドパイプに当てて滑らせると、バチバチと火花が飛び散る。「これを君たちの肛門にねじ込んであげよう。私はこれを『エレクトリック・ファック』と呼んでいる」
その言葉と共に、まだ強がる余裕を残していた方の男(因みにこっちの方が、もう1人より更にマッチョ)は、用心棒たちに俯せに押さえ込まれて、そのスタンガン状のディルドで肛門を犯されてしまう。
このシークエンスは短いんですが、汗まみれで絶叫する俳優さんの熱演や、バチバチいう電流の音響効果もあって、バイオレンス的な滋味はかなり高し。

そして、いよいよクライマックス。
もう、かなりラスト近くのネタバレまでいっちゃいますので、それが嫌な方は、以下はお読みになられませんよう。
結局、行方不明の友人を探していた残りの連中も、実は助けを求めた警察もグルだったりして、あえなく同じ囚われの身になってしまい、しかも全てを仕組んだのは友人グループの1人で、学生時代からいつもからかわれ、それに傷ついていた男の復讐だった……なんてことが明かになるんですが、ま、それはドーデモイイ(笑)。
友人の1人は射殺され、残った3人は手術室のような部屋へ連れていかれる。
2人が壁のラックに拘束され、1人は全裸で手術台に縛り付けられたところで、件のいじめられっ子が、積もり積もった恨みつらみを吐いた後、「まず、プライドと生き甲斐を奪うところからスタートだ、コックを切り取れ!」と宣言。
こうして手術台の彼は、ヘンタイ映像作家に口づけされながら、電ノコで男根を切断されてしまい、それを見ながらいじめられっ子は、ズボンに手を突っ込んでマスをかく……ってな展開になります。切断後、ヘンタイ映像作家が切り取った男根をつまんで、血まみれのそれにキスする……なんてカットも。まあ、作り物なのはバレバレなんですが、血糊の量とかは、スプラッタ映画さながらにドバドバ。

この後は「実は昔こーゆーことがありました」とゆー、ドーデモイイ伏線が機能して、結局「主人公は助かりました」的な、これまたドーデモイイ幕引きがあるだけ(笑)。
とまあ、そんなこんなで映画としてはロクでもない出来ですが、ヘンタイ指数だけはやけに高いので、そこいらへんのツボが合う方だったら、私同様にタップリ愉しめると思います。米アマゾンの商品ページの「この商品を買った人は……」を見ても、DVD買ってるのはゲイばっかみたいだし(笑)。
因みに、日本語による海外DVDの通販サイト、DVD Fandasiumでも扱っていました。参考までに、商品ページにリンクを貼っておきますので、興味のある方はどうぞ。



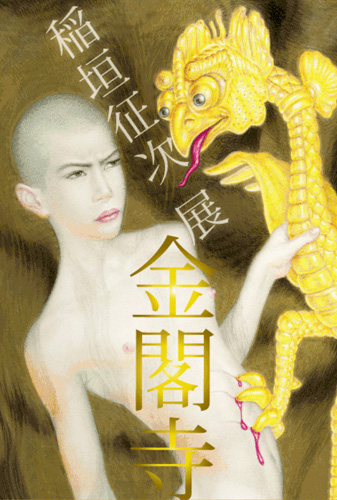
![フリッツ・ラング コレクション 怪人マブゼ博士(マブゼ博士の遺書) [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61zLIo1wLKL._SL75_.jpg)

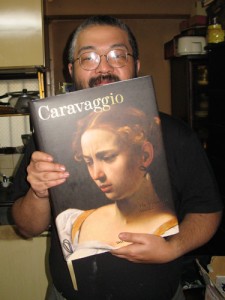
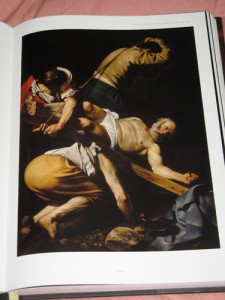
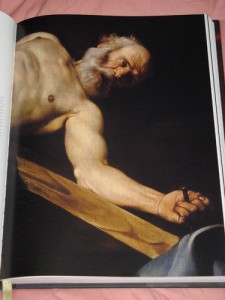
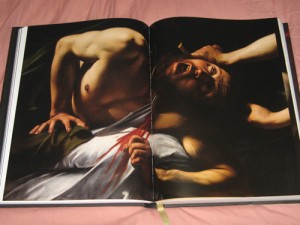


![Badi ( バディ ) 2010年 05月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51Ec-ZwmlAL._SL160_.jpg)