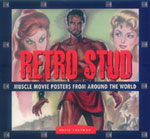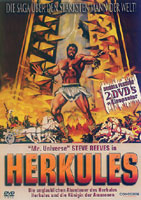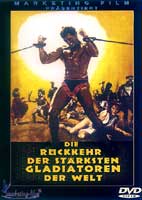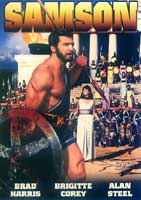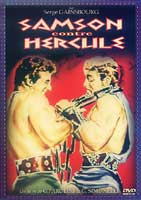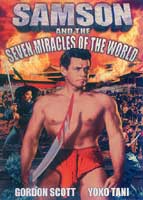![さらば美しき人 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51RD4Z502AL._SL160_.jpg) |
さらば美しき人 (1971) ジュゼッペ・パトローニ・グリッフィ “Addio, Fratello Crudele” (1971) Giuseppe Patroni Griffi |
個人的なトラウマ&偏愛映画。先日、目出度く国内盤DVDが出たので、早速購入&久々の鑑賞。
中世イタリア、美しい兄妹の近親相姦と、それが巻き起こす悲劇を描いた物語。
原作は、シェイクスピアと同時代の劇作家ジョン・フォードの戯曲『あわれ彼女は娼婦』。何でも「裏・ロミオとジュリエット」とも呼ばれるエリザベス朝演劇の名作らしいですが、これって、男優ルパート・エヴェレットの自伝的ゲイ小説『哀れ、ダーリンは娼夫?』のタイトルの元ネタでもあるんですな。
とにかく、まず絵作りが魅力的。いかにもクラシック然とした古城の佇まいと、そこに配置されたモダン・アートのオブジェを思わせるようなセットの対比は、いま見てもなかなか新鮮。騙し絵のようなベッドの天蓋、砂丘に立ち並ぶ白い旗、水に浮かぶ城、馬を乗せた筏……ちょっとピーター・グリーナウェイの諸作とか、勅使河原宏の『利休』なんかに通じるモノがあります。
カメラは、一連のベルナルド・ベルトリッチ監督とのコンビを通して、今や完全に名匠として定着した感のあるヴィットリオ・ストラーロ。画面の構成要素が極端に少ないながら、完璧な緊張感を保つコンポジション、光と影を生かした人物の陰影、抑えた色調……ああ、なんて美しいんだ。
哀感を帯びた古楽のような、美しく魅力的な音楽を付けているのは、エンニオ・モリコーネ。この古典悲劇に重厚さを与えるのに、一役買っています。ところどころ、いささか饒舌に過ぎる感も否めませんが、まあそういう部分もモリコーネの魅力のうちかな。
監督のジュゼッペ・パトローニ・グリッフィは、他には『スキャンダル 愛の罠』を見た記憶がありますが、これはさほど面白くなかったような……。女が男を監禁する話なんですが、ラウラ・アントネッリが出てたってコトと、ベッドに縛られた男の前で、少女がキーボードを狂ったように弾きまくるってゆー、ヘンなシーンしか覚えていません(笑)。
さて、映画は前述したような魅力的な世界の中で、近親相姦の悲劇が、ストイックなまでに淡々と、しかし情熱を秘めながら描かれていきます。
そしてクライマックス、ついにその情熱が爆発……っつーか暴発するんですが、そのコントラストのスゴさといったら! もう私にとってのトラウマ映画となった由縁が、このクライマックスとエンディング。
興味を削がないように詳述は避けますが、私のマンガがお好きだと言ってくださる方や、残酷美やら鮮血の美学なんて言葉に心惹かれる方、映画の後味が悪くてもぜんぜん平気っていう方だったら、是非ご覧になっていただきたい。
初見時、タイトルとスチル写真から「ロマンチックでちょっとエッチな悲恋ものかな〜?」なんて軽い気持ちで見ていた私は、このクライマックスで、もう絶句。幕切れの凄まじさにも、ズッシ〜ンと打ちのめされて、以来、忘れじの一作となった次第でして。
久々に再見したら、最初に見たときほどのダメージはありませんでしたが、それでも今回が初見だった相棒は「……怖すぎ」と申しておりました(笑)。
悲劇の妹を演じるのは、シャーロット・ランプリング。まだ二十歳ということもあり、透き通るような美しさ。まあ、若いわりには既に口角にシワがあったりしますけど、個人的にご贔屓の女優さんだから気にしないもんね(笑)。いつもと変わらぬ謎めいた魅力も漂わせながら、この作品では、まだ娘っぽい初々しさが残っているのもステキ。
脇を固める三人の若い男たち、兄役のオリヴァー・トビアスと、結婚相手のファビオ・テスティと、修道士役のアントニオ・ファルジも、それぞれの役割に合った魅力を見せてくれます。特に前者二人はヌード・シーンもあり、カメラの良さも相まって、そのスジ筋ボディが実に美しい。腰布一丁で井戸の底でのたうつオリヴァー・トビアスと、上半身裸にピチピチタイツで裸馬にまたがるファビオ・テスティには、裸身の美しさにフェティッシュな魅力も加わって、共に初見の際にかなりドキドキさせられましたっけ。皆さん、フルフェイスのおヒゲさんってのも、私的には嬉しい限り(笑)。
父親役のリク・バッタリアは、愛しのスティーヴ・リーブス様と『サンドカン総攻撃』で共演アリってのが、個人的なチェック・ポイント(笑)。
追記。オリヴァー・トビアスはチ○コも見せてくれます。今回のDVDでは、嬉しいことに無粋なボカシもなし。
このシーンを偏愛する私は大ヨロコビですが、さて、皆様はどうお感じになられるか、まあ見てのお楽しみということで(笑)。
もひとつ追記。くれぐれも、同じシャーロット・ランプリング主演の映画『さらば愛しき女(ひと)よ』と、お間違えのなきようにね(笑)。こっちはレイモンド・チャンドラー原作のハードボイルドものですんで。
![スパルタカス [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/214YN4903ZL._SL160_.jpg)