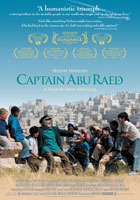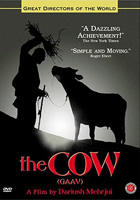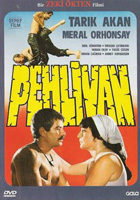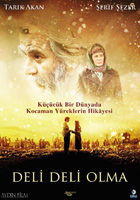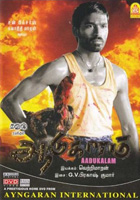
“Aadukalam” (2011) Vetrimaran
(イギリス盤DVDで鑑賞→Ayngaran)
2011年製作のインド/タミル映画。闘鶏に人生を賭ける人々の欲望や確執を描いた内容。タイトルの意味はPlayground(遊び場)。
第58回インド国家映画賞で、監督賞と主演男優賞を含む6冠に輝いた作品。
闘鶏が盛んな南インドのとある町。闘鶏はチーム制で行われ、その中でも2大チームが覇を競い、単に鶏と鶏の闘いを超えて、人間同士の争いの様相も示していた。主人公はその1チームに所属する貧しい若者で、自分も鶏を育てているものの、師匠から「この鶏はダメだから潰せ」と言われてしまう。
一方、主人公チームと対抗するライバルチームは、未だ主人公チームに勝ったことがなく、チームを率いる一家にとっては、打倒主人公チームが一族の沽券に関わる悲願となっていた。しかし主人公の師匠であるチームリーダーは、彼らが鶏のドーピング等をしているのを嫌い、挑戦を受けようとはしない。
ライバルチームは主人公チームに挑戦を受けさせるため、嫌がらせや恫喝など様々な手を仕掛けてくる。そんなある日、主人公はアングロ・インディアン(英国とインドの混血)の裕福な家庭の娘に恋をする。その恋は、一度は受け入れられたかに見えたが、実は娘には思惑があり打算のようなものだった。
ライバルチームの嫌がらせはどんどんエスカレートしていき、遂には交通事故を装った殺人にまで至る。主人公の師匠は、遂に試合を受けることを決め、交換条件として敗者は頭とヒゲを剃り、以後闘鶏から一切手を引けと突きつける。その試合の準備もあって、主人公は例の娘から金を借りる。
試合当日、ライバルチームは特別に育てた鶏を余所から輸入して挑む。主人公は、以前師匠に潰せと言われた鶏を、実は諦めきれず密かに育てており、また娘に借りた金を返済したいので、自分の鶏を試合に出してくれと師匠に頼むが、自分の目に自信がある師匠は、それを拒絶する。しかし主人公は半ば強引に自分の鶏を試合に出し、それを知った師匠は皆の前で「この試合と彼の鶏は自分のチームとは全く無関係だ!」と宣言してしまう。
ところが彼の予想とは異なり、主人公の鶏は勝ってしまう。ライバルチームは更に賞金を積んで、主人公の鶏に再戦を挑む。こうして主人公の鶏は次の試合に臨むが、一方で主人公と師匠の関係は面子を潰されたことや嫉妬などによって、目に見えない亀裂が生じてしまう。
やがてその亀裂は、試合が終わった後も主人公の気付かないところでどんどんと拡がっていき、やがては例の娘や兄弟子も巻き込む事態となり……という内容。
これはなかなか面白かった。
作りとしては、お約束のミュージカル・シーンやお笑いシーンを排した、タミル映画のニューウェーブであるリアリズム系の映画なんですが、それ系の作品がもっぱら、アンチ予定調和が過ぎてやたら暗い展開になるのに対して、本作はバランス良く纏めている感じ。
実のところ、闘鶏の試合というドラマは前半部で全て終了し(前半のクライマックスが件の試合になる)、後半はその結果引き起こされた人間同士の確執にフォーカスが移る構成になっています。
そんな中で、主人公は後半どんどん追い詰められて、にっちもさっちもいかない泥沼状態になっていくんですが、そんな中で、古いタイプのクリシェのように、追い詰められた主人公の反撃でカタルシスを出すでもなく、かといってアンチ予定調和による、神も仏もない陰々滅々とした展開にするでもなく、リアリズム的な現実の厳しさを踏まえながら、それと同時に救いも残すという、実に上手い持って行き方をしています。
クリシェのさばき方は音楽シーンも同様で、ミュージカル排除とはいえ、完全に無くすとか現実音で処理するというほど禁欲的ではなく、基本的に挿入歌によるBGM的な使い方をしながら、そこはかとなく曲に合わせて踊ったりもするといった塩梅で、そういったバランスに工夫が見られるのも面白い。
エピソードの繋ぎ等の作劇には、いささか粗いところがあり、カメラワークも、凝っているわりにはあまり効果が出ていない部分もあるんですが、本物の鶏とCGを交えた闘鶏シーンは、なかなか見せる出来映えですし、エモーショナルな場面のトゥーマッチにならない見せ方も佳良。
主人公役の男優は、およそインド映画の主演とは思えない、何とも細っこい若者なんですが、それがまた何だかニワトリっぽくて効果的。おかげで、前半の鶏同士の闘いが、後半になると人間同士の闘いに重なって見えるという、作劇的な仕掛けが実に上手く作用している感じ。
粗がない作品ではないし、リアリズムとクリシェのバランスをとろうとして、所々ちょっと中途半端になっている感もありますが(そういう意味では、前に見た“Subramaniapuram”の方がスゴい)、ストーリーの面白さや全体的な見応えが、充分それを補ってくれるといった感じです。
泥臭い系のインド映画が好きな方と、インド映画の現在に興味のある汎的な映画好きの方、どちらにも楽しんでいただけそうな佳品。
予告編。
恋の告白を受け入れて貰った主人公が有頂天になる音楽シーン。個人的には、もうちょいガッツリ踊るか、それともリアルに徹するか……と、ちょっと中途半端さを感じてしまいましたが、一般的な映画のようなリアリズム描写の枠組みの中で、いかにインド映画の伝統である歌舞を取り込むかという、そういう試行の一つとしては興味深く見られます。
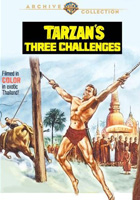
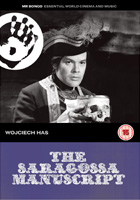

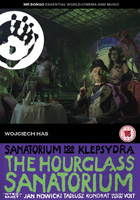


![バトル・キングダム 宿命の戦士たち [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/5178tYNS55L._SL160_.jpg)