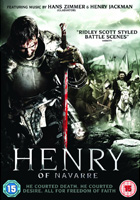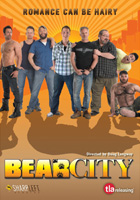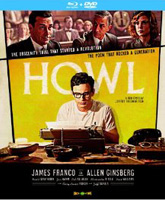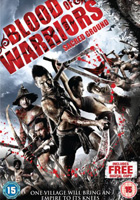“Vizontele” (2001) Yilmaz Erdogan, Ömer Faruk Sorak
(トルコ盤DVDで鑑賞、米アマゾンで購入可能→amazon.com)
2001年製作のトルコ映画。Yilmaz Erdogan監督・主演作品、共同監督Ömer Faruk Sorak。
70年代初頭、トルコの僻地の田舎村に初めてテレビが来ることになり、それを巡る人々の騒動を描いたコメディ作品で、本国では大ヒットしたそうな。
電話はロクに通じず、新聞も二日遅れで届く田舎村。娯楽はラジオと、村に唯一ある天井のない映画館だけ。そんな村に初めて《ヴィゾンテレ(テレビジョンの勘違い)》なる《絵が出るラジオ》が来ることになり、村長さんは歴史的な出来事だと大張り切り。
ところが、アンカラから受信設備と受像器を届けにきた技師たちは、この僻地に来るだけで疲労困憊。こんな田舎に一日たりともいられるかと、「高い所に設置するように」とだけ言い残して、さっさと帰ってしまう。村長さんは、何だかわけの判らないヴィゾンテレ一式を抱えて大弱り。
そこで白羽の矢が立ったのが、村人から《きちがいエミン》と呼ばれている、頭はちょっとイカれているけれども、変な仕掛けを作ったりラジオの修理だけはできるという変人。村長さんを先生と慕うエミンは、大喜びでこの大役を引き受ける。
しかしヴィゾンテレの到来が嬉しくないのが、村の映画館を経営する一家。もともと村長一家とは仲が悪い上に、ヴィゾンテレに客を奪われては大変と、宗教家を抱き込んで「ヴィゾンテレは悪魔の機械で人々を堕落させる!」と反対キャンペーンを始める。
そんな中、いよいよヴィゾンテレが高い丘に設置され、華々しいセレモニーの中、村長とエミンの手でスイッチオン。しかし映るのは砂嵐だけ。こりゃ場所が悪かったかと、別の丘に移動してみても結果は同じ。結局いくら試しても映像は映らず、村長の面目も丸つぶれになってしまう。
落ち込む村長に、エミンは「丘がだめなら、もっと高い所で試そう」と、誰も登らないような、このあたりで一番の高山のてっぺんにヴィゾンテレを持って行こうと提案。いったんは諦めかけた村長も、エミンの不屈の魂に押されて、一緒に行くことにする。
果たしてヴィゾンテレは映るのか? ……といった話。
これは面白かった。
基本的にはコメディで、テレビの出現を巡るドタバタ劇なんですが、それだけではなく合間合間に、徴兵された村長の息子と村の娘の仄かな恋愛とか、村の子供たちの悪戯風景とか、飲んだくれの夫に顧みられない妻の悩みとか、微笑ましかったり、しんみりしたり、切なかったり……といった、様々なエピソードがぎっしり詰め込まれている。
キャラクターも、きちがいエミン(=監督&脚本の人)と人の良い村長さんを筆頭に、出征した息子が心配でたまらない村長の妻とか、アンカラかぶれで女好きでホラ吹きの映画館一家の息子とか、どもりの宗教家とか、スイカ売りのデブとその妻とか、ひと癖もふた癖もある連中が勢揃いで、しかもそれらが皆、いずれも愛すべき人物に描かれている。
民族要素の色濃い軽快なテーマ曲を初め、音楽も実にご機嫌。
ただ、一つ大いにビックリしたのが、ドタバタやペーソスで笑わせて、二段オチまで用意して、たっぷりハッピーな気分にさせておいて、しかしラストで一気に急転直下、思っくそシビアな展開になったこと。
「うわぁ……ここまできて、この終わり方?」と、しばし呆然。
いちおう、この急転直下のエンディングがあるおかげで、実はこの映画は、笑わせて楽しませるだけではなく、あちこちに仕掛けられていた風刺性……文明の利器の持つ意味とか、宗教と世俗、伝統とモダン、都会と田舎の対立とか、トルコという国の置かれている状況とか、そういった諸要素が一気に深みを増すという効果があるんですが、それにしても、それまでが楽しすぎたせいもあって、このエンディングには一瞬頭が真っ白に……。
というわけで、思いっきり楽しいコメディ映画なのに、同時に何と言うか、無常観漂う悲劇でもあったりするので、何とも複雑な後味に。
聞くところによると、トルコ映画ではそういうのは珍しくないらしんですが、なんかちょっと……慣れないと消化に悪い、みたいな感じではありました。
しかし、そんな「複雑な後味を覚悟」という前提付きで、それでも実に面白い一本ですので、一見の価値はありのオススメ作品です。IMDbでも7.8点という高評価。
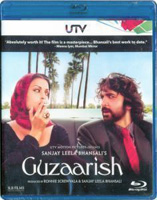
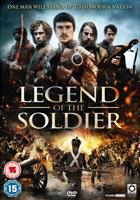
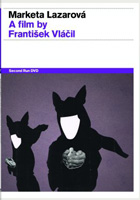

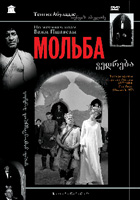

![アイアンクラッド [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/510f1W2M2tL._SL160_.jpg)