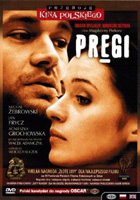『冷酷処刑人 ~父なる証明~』(2008)スティーヴン・カストリシオス
“The Horseman” (2008) Steven Kastrissios
(日本盤DVDで鑑賞→amazon.co.jp)
2008年製作のオーストラリア映画。娘を亡くした父親が、娘の死に関わった人物を捜し出し、一人ずつ処刑していくが…というスリラー。
B級スプラッター・ホラーかと思いきや、意外とマジメな作りでした。抑えた静かなシーンと鮮烈なバイオレンスがサンドイッチになった構成で、演出も佳良。ドラマの緩急やコントラストが魅力的で、けっこう作品世界に引き込まれます。
ストーリーとしては、けっこう手垢のついた内容で新味はないものの、サイドエピソードを絡めたり、程々にツイストを入れたり、省くところはバッサリ省いたり、適度に回想を配したり…と、全体のバランス感覚が良く、構成的にも冗長さを上手く回避しているので、これまたなかなか面白い。
バイオレンス描写は、けっこう即物的というか肉体的というか……特殊メイクでゲロゲロなものを見せるわけではなく、見せ物感覚で過剰なわけでもないのに、生々しい迫力や痛みを感じさせる演出で、けっこう見ていて肩に力が入ります。
役者さんもいずれも佳良で、全体的なクオリティも上々なので、興味のある方なら見て損はないでしょう。
責め場関係。まず基本的に、手がかりを探す父親→関係者発見→拷問して他の連中の居所を吐かせる→そいつを発見→拷問して別のヤツの居所を吐かせる……という繰り返しなので、わりと映画の全編に渡って、責め場はあちこち登場します。返り討ちにあって、逆に自分が拷問されるというお約束展開もあり。
で、このおとっつぁんなんですが、素人さんにしてはヤケに拷問方法がヘンタイちっくというか(笑)……映画見ながら「あれ、私こんなシーン、マンガで描いたことあるなぁ」なんて思うこと、数回。具体的には(ネタバレ気味なので白文字で)サオだかキンタマだかにポンプで空気を注入するとか、ペニスに釣り針を引っかけてクンクンするとか、乳首をペンチで引き千切るとかいった拷問が出てきます。
というわけで、そこそこエグくても大丈夫とか、逆に、残酷男責め大好きという人には、かなりオススメできる一本でした。
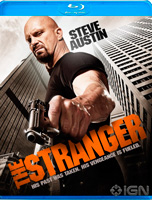

『スティーヴ・オースティン ザ・ストレンジャー』(2010)ロバート・リーバーマン
“The Stranger” (2010) Robert Lieberman
(米盤Blu-rayで鑑賞→amazon.com、日本盤DVDあり→amazon.co.jp
)
2010年製作のオリジナル・ビデオ映画。愛しのストーンコールド・スティーヴ・オースティン様主演の、記憶喪失の男がFBIに追われながら自分の過去を探っていき……みたいな内容のアクション映画なんですが、実際の出来の方はこういう具合だというので、もう多くは期待せず完全に責め場だけ目当てで見ました(笑)。
というわけで、メキシコ警察に捕まったスティーヴ・オースティンが、上半身裸で椅子に縛られて、ナイフでスパスパやられるシーンは、実に良うゴザイマシタ(笑)。クレーンに両手縛りで吊るされて、角材でタコ殴りされるシーンは、責めのアイデア自体はオッケーなんですけど、着衣なのが残念(笑)。
ま、しょ〜もない感想ですが、見所はそれだけってことで(笑)。
因みにFacebookで「見所はスティーヴ・オースティンの身体だけだった〜!」と愚痴ったら、「ヤツの映画はいっつもそうだよ!」と外国の方からもご賛同いただけました(笑)。

“A Serbian Film” (2010) Srđan Spasojević
(イギリス盤Blu-rayで鑑賞→amazon.co.uk、日本のアマゾンでも購入可能→amazon.co.jp
2010年製作のセルビア映画。原題”Српски филм / Srpski film”。
引退して幸せな家庭を築いていた元ポルノスター男優が、アートなポルノ制作という誘い文句と高額の報酬に釣られて復帰したところ、とんでもないゴアゴアな罠に嵌められて…という内容。
内容のアモラルさとエログロさに、かなり物議をかもした映画らしいですが、まあ確かに過激で鬱々な内容です。私が見たのは英盤Blu-rayで、これは一部カットされたバージョンらしいんですが、それでも内容は「とにかく酷い話に!」ってな感じで、いわゆる鬼畜描写がテンコモリ。
どんだけエグいシーンがあるかは、ちょいとググればレビューが出てくるので割愛しますけど、正直なところポルノグラフィの持つ即物的な力は、一般映画(とはいえイギリス盤でも18禁指定なんですが)には超えられない壁なので、そういう意味ではこの映画も、そこはクリアできていない印象。そんなわけで、内容のエクストリームさと同時に、映画の限界のようなものも同時に感じてはしまいましたが、それでもかなりギリギリまで迫ろうとする意欲とか、徹底してブレない姿勢とかは好印象。
ただ、事前に覚悟していたほどは、見終わったときにイヤ〜ンな気分にはならなかったなぁ。確かに容赦ない鬱展開だし、スゴいっちゃあスゴいんだけど、ぶっちゃけ私は、これ見て引くほど良識的な人間じゃないし、このくらいの展開だったら自分でも考えつくしな〜……ってな感もあり(笑)。
でも、一緒に見た相棒は、見終わった瞬間「ひっどい話だね!」と憤慨していました(笑)。
男責めとしては、具体的なアレコレよりも、シチュエーション的にグッとくるものがあり。
主人公のポルノ男優は、一服盛られて意識を失ってしまい、正気にかえってから撮影されたビデオを見て、自分が何をしていたかを知るんですが、それが、麻薬と媚薬漬けにされて(以下ネタバレ含むので白文字で)女を犯しながら殺したり、男にカマを掘られていたり、何とか逃げ出したものの発情を抑えられなくて路上でズリセンぶっこいたり、自分のチンコを切り落とそうとしたり、まだ幼い実の息子のカマを掘っていたり……ってな具合で、ここいらの展開は良かったな〜。罠にはめられた男が酷い目にってのも、媚薬で発情アニマル化ってのも、どっちも大好物のネタなので(笑)。
因みに、イギリスではR18指定になっただけあって(ちょっとアレな情報なので、また白文字)、作り物の付けチンポコですけど、ブラ〜ン状態もフル勃起状態もガン見えでした(笑)。
そんなこんなで、とにかくアモラルで鬱々な、極めて露悪趣味的な映画なので、例えホラー好きの方でも、流石にこれはキツいというのはあるかも知れません。
でも、氏賀Y太先生や早見純先生のマンガが好きな方だったら、一見の価値はありかと。
《追記》『セルビアン・フィルム』の邦題で日本公開&ソフト化されました。
![セルビアン・フィルム 完全版 [Blu-ray]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/513WhOQ1HZL._SL160_.jpg) |
セルビアン・フィルム 完全版 [Blu-ray] 価格:¥ 4,935(税込) 発売日:2012-07-27 |
![セルビアン・フィルム 完全版 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51%2BxRJV%2BfYL._SL160_.jpg) |
セルビアン・フィルム 完全版 [DVD] 価格:¥ 3,990(税込) 発売日:2012-07-27 |
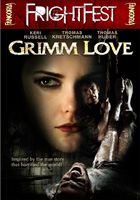

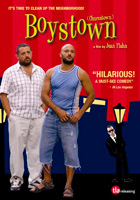


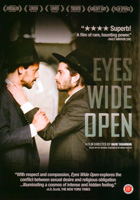
![デッドロックII [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51qNpfUOJ1L._SL160_.jpg)
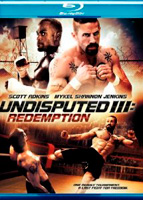
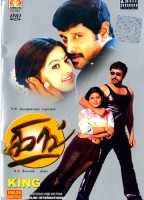
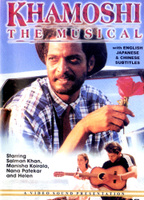
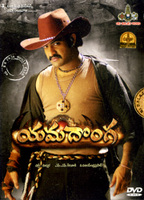
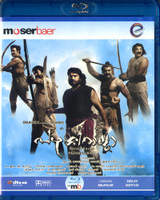
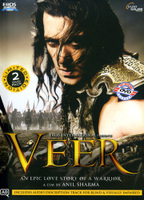

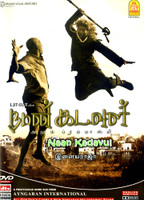

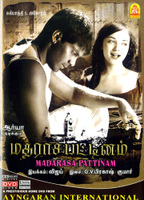
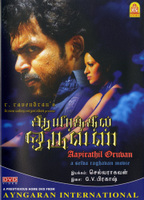
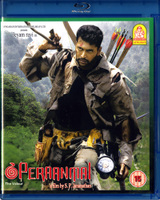
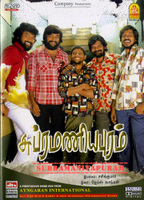
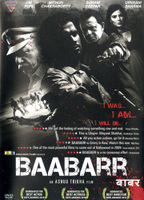
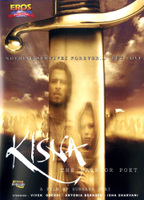
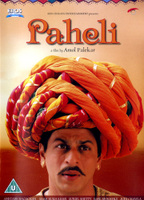

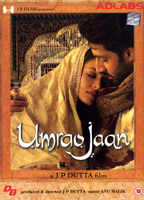

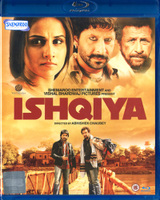



![バンディット 前編:義賊ヤノシークの誕生 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51E-beCsr3L._SL160_.jpg)
![バンディット 後編:英雄の最期 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51NODyfb%2BFL._SL160_.jpg)
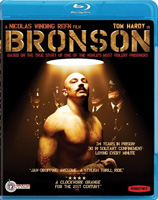
![ブロンソン [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/517AZq-zlKL._SL160_.jpg)
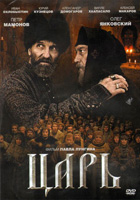
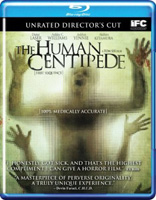
![ムカデ人間 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41FGABiIFCL._SL160_.jpg)
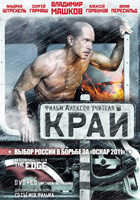
![爆走機関車 シベリア・デッドヒート[DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51egkz0npML._SL160_.jpg)
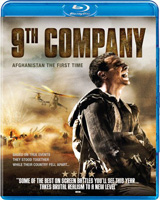
![アフガン [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51pbH9ccO2L._SL160_.jpg)



![7 DAYS リベンジ [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51BN0HqqxEL._SL160_.jpg)