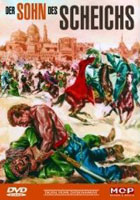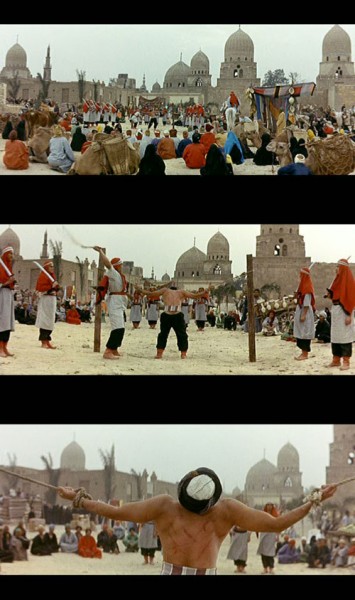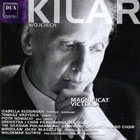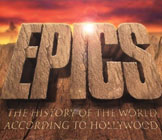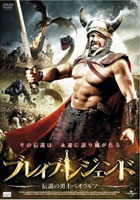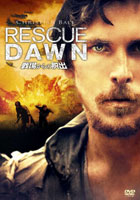
『戦場からの脱出』(2006) ヴェルナー・ヘルツォーク
“Rescue Dawn” (2006) Werner Herzog
ヘルツォーク監督作品でクリスチャン・ベイル主演なのに、劇場公開なしのDVDスルーとは悲しいご時世。まあ、DVDで出ただけ良しとしますか。
B級映画みたいな邦題と一緒に、パッケージにはデカデカと「戦争アクション!!」なんて書いてあります。
確かに、ストーリーだけ抜き書きすると、ヴェトナム戦争で撃墜された飛行機のパイロットが、拷問されたり捕虜収容所に入れられたりして、とっても辛い目に遭いつつ、何とかそこを脱出するけど、今度は過酷なジャングルを生き抜かなければならず……という具合で、確かにB級アクション映画っぽいんですけどね。
とはいえ、やっぱりヘルツォーク。
いくら『コブラ・ヴェルデ』以降、何となくフツーっぽくなった感があるとはいえ、間違ってもコレは「戦争アクション映画」ではない。「戦争映画」ですらないかも。
というのも、この映画における戦争や国家、政治や思想、敵や戦いといった要素は、単なる状況以上の意味はなく、映画のテーマとは全く関係ないのだ。では、テーマは何かというと、やはりヘルツォーク十八番の、大自然と拮抗しうる力を持つ、人間の狂気なわけです。
そういうわけで、ヘルツォーク好きなら、見所はイッパイ。
まず、冒頭のスローモーションによる空爆シーンからして、一気に魅了される。『アギーレ 神の怒り』の登山とか、『緑のアリの夢見るところ』の竜巻同様、「うぉ〜、ヘルツォークの映画だ〜っ!」って感じで、もうそれだけで嬉しくなっちゃう(笑)。
本編に入っても、美麗で荘厳な自然描写(粛然とした前半も良いけど、やはり後半の圧迫感が、もうヘルツォークならでは)、徹底したリアリズム(捕虜たちの痩せっぷりとか、もうハンパねぇです)、緊張感と詩情の対比(蝶と犬の使い方が良かったなぁ)、等々、やっぱり素晴らしい。
音楽はクラウス・バデルトなんですが、往年のヘルツォーク組で今は亡きフローリアン・フリッケ(ポポル・ヴー)の曲が、1曲使われていたのも嬉しかったなぁ。
バデルトのスコアも悪くはないんだけど、例えばラスト・シーンで、余りにも単純な「実話を元にした感動作!」みたいな、いかにも風のテンションを盛り上げるスコアを付けちゃっているあたりは、正直ちょい疑問を感じました。主人公のセリフと暗転後のテロップによって、この映画で描かれているのは、「常軌を逸した生命力を持った人間の凄さ(或いは、異様さ)」だということが明示されるんですけど、この音楽だと「アメリカ万歳!」か「英雄の帰還!」みたいに、テーマをミスリードしてるみたい。
まあ、この部分の音楽に限らず、全体として瑕瑾がないかというと、残念ながらそうではない印象はあります。
主人公は、『アギーレ』や『フィッツカラルド』、あるいは『カスパー・ハウザーの謎』の主人公同様に、一般の規範や価値観から完全に逸脱した、常軌を逸した存在なんですが、それが充分に表現されていたかというと、いささか疑問が残る。
主役のクリスチャン・ベイルは、文句なしに上手いし、役になりきった体当たり演技もあって、狂気と裏腹のエクストリームさもあるんですが、いかんせん、肝心の「生命力」があまり感じられない。キャラクターとしての「強さ」が、いまいち足りていないというか。
また、前述したように、ストーリーを抜き出すと、シンプルな娯楽作の筋立てに近すぎること(まあ、実話なんだから仕方がないけど)も、結果として、映画の本質を曖昧にしてしまっているような気がします。
そういう感じで、かつてのヘルツォーク作品を知っていると、共通する要素が多い分、どうしても比較もしてしまって、ちょっと「弱い」感じがしてしまう。『神に選ばれし無敵の男』のときは、逆に共通項が少ない分、問答無用で「傑作!」と思えたんですけど。
でも、一本の映画として見れば、充分以上に見応えのある佳品なので、ヘルツォークのファンも、そうでない人も、ご覧になる価値は充分以上にあるかと。
『戦場からの脱出』(amazon.co.jp)
最後に、いつものアレ系(笑)の追補。
POWの映画なので、いちおう拷問シーン(縛られて牛に引きずられたり、逆さ吊りにされて顔に蟻塚を括り付けられたり)もありますが、リアリティや無惨さはともかくとしても、エロティックな興趣はゼロですので、ソッチ系好きの方は、あまり期待なさらないよう。
ヴェトナム戦争POWモノの責め場が目当てだったら、『ランボー』シリーズ(スタローンがあんまり好きじゃないので、実は良く知らない)とか、チャック・ノリスの『地獄のヒーロー』シリーズとか(『3』の責め場はお気に入り)、あるいはもっとB級の『炎の戦士ストライカー』だの
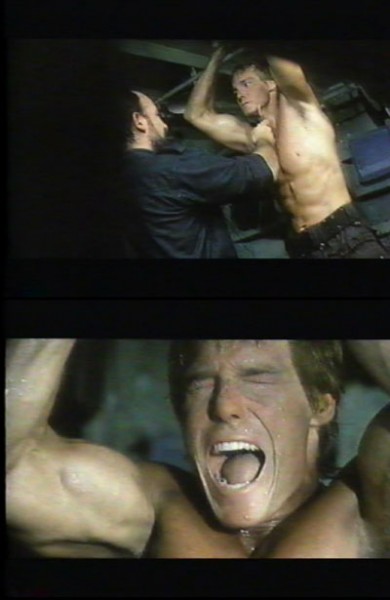
『ストライク・コマンドー』だの
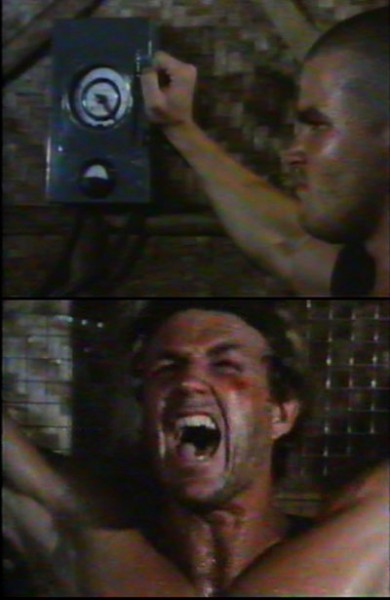
『怒りのコマンドー』だの、
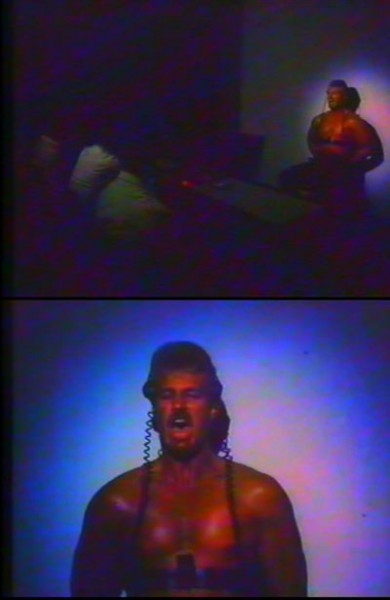
もうちょい映画的にマトモなところでは『ハノイ・ヒルトン』とか
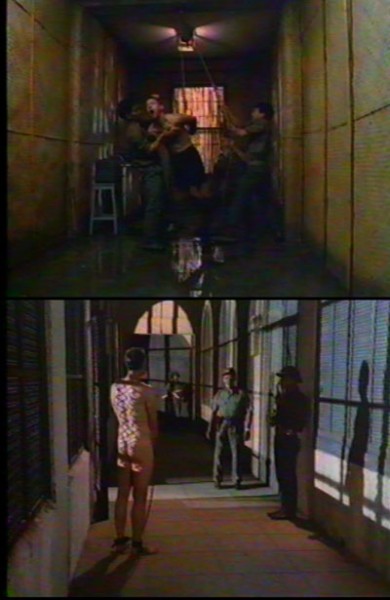
『極秘指令/グリーンベレーを消せ!』とかを、

ご覧になった方がヨロシイかと(笑)。