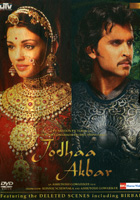
“Jodhaa Akbar” (2008) Ashutosh Gowariker
またまたインド映画です。
16世紀のムガール帝国の第三代皇帝、ジャラールッディーン・ムハンマド・アクバルの、若き日の愛と戦いを描いた一大スペクタクル史劇。監督は、『ラガーン』のアシュトーシュ・ゴーワリケール。
若くして即位したジャラールッディーンは、重臣の傀儡的な存在として周囲の王国を征服していくが、やがて長じて実権を取り戻し、政略結婚としてラージプートの王族の姫、ジョダーを娶ることになる。
しかし、ムスリム(イスラム教徒)のジャラールッディーンに対して、ヒンドゥー教徒ジョダーは、婚姻にあたって、「改宗を要求しないこと」と「王宮内にヒンドゥー教の祭壇を作ること」という、二つの条件を出す。ジョダーの父王を含めて、周囲はその条件に動揺するが、ジャラールッディーンはそれを受け入れる。
こうしてジョダーは、王妃としてアーグラー・フォートの王宮に入るが、夫となったジャラールッディーンには、まだ心を開いていなかった。また王宮には、ヒンドゥー教の王妃を快く思わない勢力や、税金を横領する悪徳一味などもいた。
やがて、ジャラールッディーンとジョダーは、次第に互いに心を開いていくが、ジャラールッディーンの乳母は、王を息子のように愛するあまり、その間に入り込んだ王妃を快く思わず、何とか二人の仲を裂いて王妃を追放しようと画策する。いっぽう砦の外では、ジャラールッディーンの義弟が兄の地位を狙い、ジョダーの幼なじみの従兄も巻き込んで謀略を巡らす。
果たして、ジャラールッディーンとジョダーの運命やいかに?
ってのが、おおまかな内容です。
いちおう歴史劇の形をとっていますが、監督のインタビューなどを聞いていると、実のところはフィクションの要素も多いようです。特に、王妃ジョダーに関しては、映画に描かれている姿は、かなり民間伝承的なものらしい。
また、叙事のスタイルも、歴史を俯瞰するタイプではなく、メインのフォーカスはジャラールッディーンとジョダーのロマンスに置かれている。そういう意味では、ハリウッド史劇で例えると、ジョセフ・L・マンキウィッツの『クレオパトラ』とか、キング・ヴィダーの『ソロモンとシバの女王』なんかに感触が近い。
ただ、それら二つがいずれも、ロマンスの部分と歴史的叙事の部分に乖離を見せていたのに対して、この”Jodhaa Akbar”では、ヒーローとヒロインの関係性の変化が、そのまま政治的なパワーゲームに反映されていくという構造なので、作劇としてはより自然で楽しめるものになっています。
まあ、モノガタリとしては、すこぶるつきで面白い。ジョダーと従兄の仄かな恋とか、ジャラールッディーンの人知れぬ悩みとか、乳母の盲愛とか、権力欲と金銭欲に駆られた悪役どもとか、様々な要素と様々なキャラクターが絡み合い、一度見始めたら先が気になって止まらない系の大河ドラマになっています。
エピソードや見せ場も、一大戦闘シーンもあれば決闘もあり、華麗な歌舞もあればドロドロした女の戦いもあり、スペクタクル史劇とミュージカル映画とロマンス映画と昼メロがゴチャマゼになったような、インド映画ならではのテンコモリの娯楽要素が、めいっぱい楽しめます。
加えて、テーマとなっている宗教の違いを超えた人々の和合というものは、インド国内の問題はもちろんのこと、今日の世界全体が抱えている命題の一つでもあるので、そういった同時代性のある制作姿勢にも好感度は大。
画面の物量とスケール感は、とにかく圧倒されるの一言。
出てくる宮殿や砦の数々、モブシーンの人の多さ、衣装やインテリアで見られる極彩色の色彩美、何から何まで、ひたすらゴージャスで贅沢。まあ、どのくらいスゴいかというのは、例によって公式サイトをご覧あれ(笑)。
中でも特筆したいのは、ジャラールッディーンがそれまでの征服者としてだけではなく、統治者としても民衆から受け入れられ、「アクバル(偉大なる)」の尊称を送られ、人々から讃えられる、”Azeem-O-Shaan Shahenshah”という超弩級の一大群舞。ここは本当にスゴい! イマドキのハリウッド映画では全く見られなくなった、ハレの祝祭空間としての一大スペクタクルが、8分以上に渡って、これでもかこれでもかと繰り広げられます。
いや〜、前に『ナルニア国物語/第1章:ライオンと魔女』のときにも書きましたが、今回のこれは、マンキウィッツ版『クレオパトラ』のローマ入場シーン以来の満足感。見ていて、感激で涙が出ちゃいました(笑)。自宅のテレビで見てこれなんだから、もし劇場で見ていたら失禁していたかも(笑)。
ロマンティックなシーンも、総じて良い出来。ウットリさせるという点では、文句なしの美しさ。例によって、キスシーンすらないんですが、二人が初めて真の夫婦となった場面での、詩的な歌詞のミュージカル・シーンなんか、下手なベッドシーンなんかよりよっぽどステキです。
一方、戦闘シーンなんかは、正直あまり良い出来ではないです。
物量は充分だし、CGIもそこそここなれているんですが、演出が近年のハリウッド製スペクタクル的な類型でしかなく、しかも決して上手くはない。一対一の剣戟も、殺陣が悪いのかカット割りが悪いのか、迫力にも緊張感にも欠けて、どうにもさまにならない。
風景のスケール感とか、たっぷり引きのある構図を埋め尽くすモブとか、戦象の大群とか、鎧兜の美しいデザインとか、魅力的な要素はテンコモリなのに、この演出の締まらなさは、何とも惜しい限り。ただ、戦闘シーンで「大砲に装填された砲弾の一人称カメラ」ってのが出てきまして、ここだけは往年のダリオ・アルジェントの発想みたいで、ちょっと愉快でした(笑)。
役者は、ジャラールッディーン王役にリティック・ローシャン。我が家では、先日『アルターフ 復讐の名のもとに』を見て以来、「鼻」というニックネームで親しまれていますが(笑)、今回は口ヒゲ付きということもあって、私としては充分にカッコよく感じられました(笑)。
演技の方も、大帝国の皇帝らしい力強い威厳と、恋する青年的なナイーブな側面を、共に良く好演していて二重丸。エピックのヒーローとしては、文句なしのキャラクターを見せてくれます。身体一つで象と闘うシーンでは、ノリが完全にソード&サンダル映画と同じだったのも、個人的には嬉しかった(笑)。
あと、この方、かなりのマッチョなんですが、今回は心を開かない妻の気を惹くために、わざわざ妻の部屋の前で上半身裸になって剣技(……なんですけど、やってることはボディービルのポージングみたいなもん)をするという、男心が可愛らしいシーンがあります(笑)。ここは、男の肉体美の見せ場として、マッチョ好きなら見て損はなし。もう一人、ジャラールッディーンの義弟役の男優さんも、かなりのマッチョ。入浴シーンで、目が釘付けになりました(笑)。
ヒロインのジョダーは、アイシュワリヤ・ラーイ。”Devdas”で、その美貌の虜になって以来、私も相棒も大ファンの女優さん。相変わらずお美しいけれど、ちょっとお腹のあたりに、お肉がついたかな?
演技的には、美しさ以外の見所は、あまりなかったような。剣戟もあるんだけれど、前述したように、この映画のアクション・シーンは、全般的にあまり良くないので……。ただ、キャラクターとしては良く立っていて、王様との恋路を応援して、幸せになって欲しいと願う気持ちには、充分させてくれます。
クレジットでアイシュワリヤ・ラーイ・バッチャンとなっていたので、「おや、結婚したの?」とビックリしたんですが、調べてみたらアミターブ・バッチャンの息子と結婚したんですね。
アイシュワリヤ・ラーイといえば、去年フランスに行ったとき、飛行機の中で彼女が主演している”The Mistress of Spices”という、ラッセ・ハルストレムの『ショコラ』のスパイス版みたいな映画を見まして、これは英米合作映画だし、ひょっとしたら単館上映とかがあるかも……と、期待してたんですけど、けっきょく公開もソフト化もされずじまいみたい。残念!
音楽は、A・R・ラフマーン。前述の”Azeem-O-Shaan Shahenshah”を筆頭に、歌曲では相変わらず良い仕事をしています。変わったところでは、カッワーリのヒンディー・ポップ版といった趣の曲(映像では旋回舞踏も出てきます)なんかもあり。
劇伴の方は、壮大なストリングスや混声コーラスに、ブラスや打楽器のアクセントといった、ハリウッド史劇のパターンと同じタイプで、民族性は意外なほど薄い。まあ、可もなく不可もなしといったところですが、ハリウッド製の方がよほどエキゾチックだというのは、ちょっと面白いですな。
DVDはNTSC、リージョン・コードはフリー。本編ディスク2枚と特典ディスク1枚の3枚組。
特典の内容は、監督やスタッフ、キャストなどのインタビュー、削除シーン、予告編、PR映像各種、テキストによる時代背景の解説など。削除シーンで見られる、野に住む賢者のエピソードが、いかにも民間伝承っぽくて面白かった。これ、インド人にはお馴染みの話なのかな?
ただ、ソフトとしては大きな難点が、一つあります。パッケージはとっても豪華でキレイなんだけど、肝心の中身が……。新作映画のソフトで、シネスコ画面をいまどき非スクィーズで収録って……。画質そのものは決して悪くはないんだけど、解像度が足りないのは何ともしがたい。
ま、インド映画のDVDでは、こーゆー難点は今に始まったことじゃないけど(笑)。
【追記】後に出たBlu-rayは、前述のDVDに対する不満も全くなく、文句なしの高画質でした。
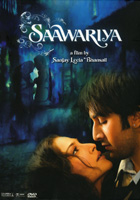



![木靴の樹 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51mz2-QTF5L._SL75_.jpg)
![シベリアーダ [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51Z3noFjxUL._SL75_.jpg)
![ペレ [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/21ESRAK437L._SL75_.jpg)
![アルターフ 復讐の名のもとに [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/518YZK8K03L._SL75_.jpg)
![わすれな歌 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51kQSosoROL._SL75_.jpg)
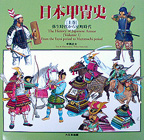





![ランカスカ海戦 ~パイレーツ・ウォー [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61NJ7-6MvCL._SL160_.jpg)


